道後温泉地区の活性化の基本方針策定
 老朽化や耐震性が懸念される築一二○有余年の道後温泉本館の改修を含む同地区の活性化の基本方針が示された。要旨は、以下3点
老朽化や耐震性が懸念される築一二○有余年の道後温泉本館の改修を含む同地区の活性化の基本方針が示された。要旨は、以下3点
①.本館改修時期は愛媛国体終了後とし、工事期間中は、観光客の落ち込みを極力抑える為、営業しながらの改修とし、極力工期の短縮をはかる (7~9年)、又、伝統的建築物ゆえに作業そのものを見せる工夫をし、安全を確保しつつ交通への影響の緩和に最大限努める。
二.代替施設が期待される (仮称)椿の湯別館の来秋オープンを目指す、と同時にその活用と誘客対策に取り組む (具体的にはオープンと同時に民間活力が発揮できるよう指定管理者制度の導入を実施)
三.一昨年から実施し、好評を頂いている温泉とアート事業をコラボした道後オンセナートは、現在、アート事業は継続する中で、(仮称)道後オンセナート二○一八を予定している。来年の愛媛国体や子規・漱石の生誕一五○年記念事業等との相乗効果をみすえ、来年年9月にプレオープン、再来年4月から翌年3月までの19ケ月間の長期開催を予定している。
日本最古を誇る道後温泉は本市の貴重な歴史遺産として市民に大切にされてきた.その象徴とも言える本館は約一二〇年前に初代道後湯之町町長 伊佐庭如矢 (いさにわゆきや)が多くの問題を抱えながらも改築を成し遂げたもの。又、如矢は松山城の公園化や道後鉄道の開設など、百年先をみすえた道後のまちづくりを進めた。如矢は 「 道後は、今のままでも10年、20年は栄えるだろう。しかし、今後もっと鉄道や航路が発達したら将来の状況は変わる。そうしたなかで百年後に道後温泉が同じように栄えている保証はない。百年経っても真似ができないものを造ってこそ意味がある。人が集まれば町が潤い、百姓や職人の暮らしも良くなる将来の道後温泉のために協力して欲しい 」 と、誠心誠意、町民を説得してこの偉大な事業を完成させた。
時代は異なれどまちづくりへの思いは同じ、この言葉を肝に銘じ、道後の取り組みを注視して行きたい。
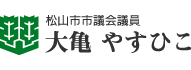


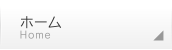
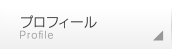
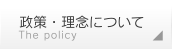


 水問題は松山市のアキレス腱、本市の水源は、度々、取水制限を受ける石手川ダムと2ケ月程度の少雨傾向で大幅な水位の低下となる重信川水系の地下水の2つしかなく、ここ20年間のうち15年間で、渇水対応が強いられてきた。こうした中、本市が進めてきた西条分水の根拠となっている長期水需給計画が策定から10年を経過したことから、検証・見直され、平成37年度目途の新たな計画の概要及び必要水量(日量)を公表した。人口減少や節水の推進により、17千トン需要量は減少したが、気候変動等の都市リスクの低減や高層住宅への直接給水等、生活環境の改善分として9千トン増し、4万トン(現行は4万8千トン)に縮小すると公表した。当計画は、学識経験者、事業者、市民の代表で構成する検討委員会、市議会の特別委員会で意見聴取し、パブリックコメントを経て、今年度中に市長に提出される見通し。今回の見直しにより、市は必要水量は減るが、現時点で西条分水の方針変更はないとしている。しかしながら、議会内でも、現計画が策定された10年前には、大多数の議員が賛同し、西条分水推進の決議を表明したが、その後、懐疑的もしくは否定的な勢力も増えている。又、水利権者である愛媛県の仲介により、当事者間で協議の場が設けられ、“西条の水を守る”という目的は共有できたものの、水源を有する西条市では、市民感情もあり、分水については頑なに反対の意向を崩していない。依然、複雑で困難な情勢の中、市政の最重要課題としての議会の判断、市長の手腕が問われる
水問題は松山市のアキレス腱、本市の水源は、度々、取水制限を受ける石手川ダムと2ケ月程度の少雨傾向で大幅な水位の低下となる重信川水系の地下水の2つしかなく、ここ20年間のうち15年間で、渇水対応が強いられてきた。こうした中、本市が進めてきた西条分水の根拠となっている長期水需給計画が策定から10年を経過したことから、検証・見直され、平成37年度目途の新たな計画の概要及び必要水量(日量)を公表した。人口減少や節水の推進により、17千トン需要量は減少したが、気候変動等の都市リスクの低減や高層住宅への直接給水等、生活環境の改善分として9千トン増し、4万トン(現行は4万8千トン)に縮小すると公表した。当計画は、学識経験者、事業者、市民の代表で構成する検討委員会、市議会の特別委員会で意見聴取し、パブリックコメントを経て、今年度中に市長に提出される見通し。今回の見直しにより、市は必要水量は減るが、現時点で西条分水の方針変更はないとしている。しかしながら、議会内でも、現計画が策定された10年前には、大多数の議員が賛同し、西条分水推進の決議を表明したが、その後、懐疑的もしくは否定的な勢力も増えている。又、水利権者である愛媛県の仲介により、当事者間で協議の場が設けられ、“西条の水を守る”という目的は共有できたものの、水源を有する西条市では、市民感情もあり、分水については頑なに反対の意向を崩していない。依然、複雑で困難な情勢の中、市政の最重要課題としての議会の判断、市長の手腕が問われる 2008年に閉館したラフォーレ原宿松山跡地の再開発が完了し「アエル松山」としてオープンした。1~2階が商業施設、3~4階がブライダル、5~13階がホテル、若者や女性客、更には観光客も集うスポットとしての再生を期待したい。又、花園町東地区では、アーケードの撤去、電線の地中化に続き、統一化した景観(ファザード)整備がはじまっている。更に、民間の再開発がとん挫し、長年塩漬けとなっていた銀天街L字地区は地元・行政の再開発に向けた協議会がたちあがった。堀之内~花園町、まつ地下、市駅、銀天街、大街道、ロープウェー街、そして道後を繋ぐ地域は野志市政の重点整備エリアだ。
2008年に閉館したラフォーレ原宿松山跡地の再開発が完了し「アエル松山」としてオープンした。1~2階が商業施設、3~4階がブライダル、5~13階がホテル、若者や女性客、更には観光客も集うスポットとしての再生を期待したい。又、花園町東地区では、アーケードの撤去、電線の地中化に続き、統一化した景観(ファザード)整備がはじまっている。更に、民間の再開発がとん挫し、長年塩漬けとなっていた銀天街L字地区は地元・行政の再開発に向けた協議会がたちあがった。堀之内~花園町、まつ地下、市駅、銀天街、大街道、ロープウェー街、そして道後を繋ぐ地域は野志市政の重点整備エリアだ。 松山海洋少年団が緑綬褒章(りょくじゅほうしょう:自ら進んで社会に奉仕する活動に従事し徳行顕著な者)を受章し市長に受賞報告した。昭和45年結団以来、毎年、訓練場所の梅津寺海岸の清掃活動を続けてきた功績が今回の受章理由。海を舞台に、様々な体験を通じて健全な人材育成を目的とする同活動は、今や少子化や趣味の多様化等、団員確保が困難な状況で、最盛期は100名を超えていましたが、現在は30名弱、私は後援会として関わっており、四方を海に囲まれた海洋国という地勢上、海洋資源や貿易、安全保障等、海の重要性は日々増しており、海事思想を普及・啓蒙する意味からも、今回の受賞を機に、関係者が協力し活動を盛り上げて行きたい
松山海洋少年団が緑綬褒章(りょくじゅほうしょう:自ら進んで社会に奉仕する活動に従事し徳行顕著な者)を受章し市長に受賞報告した。昭和45年結団以来、毎年、訓練場所の梅津寺海岸の清掃活動を続けてきた功績が今回の受章理由。海を舞台に、様々な体験を通じて健全な人材育成を目的とする同活動は、今や少子化や趣味の多様化等、団員確保が困難な状況で、最盛期は100名を超えていましたが、現在は30名弱、私は後援会として関わっており、四方を海に囲まれた海洋国という地勢上、海洋資源や貿易、安全保障等、海の重要性は日々増しており、海事思想を普及・啓蒙する意味からも、今回の受賞を機に、関係者が協力し活動を盛り上げて行きたい 城と路面電車そして漱石」、更には、最近では、くまモンとみきゃん、本市と共通点の多い被災地熊本市とは、官民含め草の根交流で結ばれています。本市議会も、毎年必ずと言っていいほど、いずれかの委員会視察で同地を訪れ、市政全般で先進的な取り組みについて比較・調査・研究させて頂いています。
城と路面電車そして漱石」、更には、最近では、くまモンとみきゃん、本市と共通点の多い被災地熊本市とは、官民含め草の根交流で結ばれています。本市議会も、毎年必ずと言っていいほど、いずれかの委員会視察で同地を訪れ、市政全般で先進的な取り組みについて比較・調査・研究させて頂いています。 正月、年頭の所感で野志市長は、2050年の松山の将来像、「松山中心市街地2050(に―まる・ご―まる)ビジョン」を披露されました。
正月、年頭の所感で野志市長は、2050年の松山の将来像、「松山中心市街地2050(に―まる・ご―まる)ビジョン」を披露されました。 交通先進地冨山を視察しました。人口42万人の地方都市ながら、市長の強力なリダーシップとLRT(新型路面電車)によるまちづくりという明確な都市ビジョンにより疲弊した中心市街地が見事に蘇り、まちは活気に満ち溢れていました。まちの中心地には、ビル街の中を静かな音色、スマートでおしゃれな外観、お年寄りや子ども、障がい者に乗り降りしやすい低床のLRTが往来し、機能性に加え、その存在自体がまちの景観の一部となっていました。坊っちゃん列車が松山城、道後温泉に次ぐ松山の景色となっているように・・・。そういった意味で住民の足、公共交通の果たす役割は大きく”まちの顔”にもなりうるような大きな存在であることを再認識しました。北陸新幹線の開通を機に、今、北陸が熱い。
交通先進地冨山を視察しました。人口42万人の地方都市ながら、市長の強力なリダーシップとLRT(新型路面電車)によるまちづくりという明確な都市ビジョンにより疲弊した中心市街地が見事に蘇り、まちは活気に満ち溢れていました。まちの中心地には、ビル街の中を静かな音色、スマートでおしゃれな外観、お年寄りや子ども、障がい者に乗り降りしやすい低床のLRTが往来し、機能性に加え、その存在自体がまちの景観の一部となっていました。坊っちゃん列車が松山城、道後温泉に次ぐ松山の景色となっているように・・・。そういった意味で住民の足、公共交通の果たす役割は大きく”まちの顔”にもなりうるような大きな存在であることを再認識しました。北陸新幹線の開通を機に、今、北陸が熱い。

