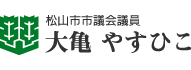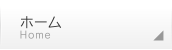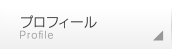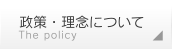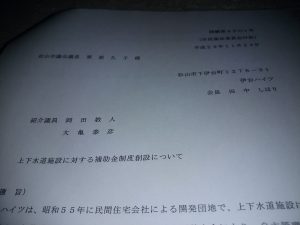ホーム > 大亀やすひこブログ
交通環境改善
長年、愛媛県交運労協で市長要望をしていた、はなみずき通りと南環状道路との交差点付近の左折車線設置工事が完成し、供用開始となった、はなみずき通りは、松山市駅や県立中央病院、高校に続く、市内中心部への基幹道路、特に通勤、通学時は、直進と左折車線が供用されており、大渋滞でした、粘り強い運動に敬意、そして市長の英断に感謝!
新芽
知人からだいぶん昔(20年前くらい)に頂いた、わが家の観葉植物の、いな蔵くん、ほとんど水も栄養液もやらず、ほったらかし、今朝、なんと、新芽を発見!どんなに厳しい環境でも、粘り強く頑張ろう、いな蔵くんに、ちなんで!
関学フェスタイン四国
黄色いハンカチプロジェクト
 私の地元星岡町では、おやじの会が中心となって防災訓練の一環として地域住民の防災意識の高揚と大規模災害時の安否確認の効率化を狙った黄色いハンカチプロジェクトを行っている。これは、大規模災害時、生存している御家庭には黄色い目印を玄関や窓等、外から見える場所に掲出していただき、掲げていない家庭への人命救助を重点化し、一人でも多くの地域の方の命を救おうという取り組みであります。自治会や公民館の役員は高齢者が中心、松山市が目指す住民自治の実現には若手の担い手の参加が必要です。そこで、地元、小学校と町内会のおやじの会の活動に最高齢者?として参加、飲みにケーションをはかりながらまちづくりについて時を忘れ深夜まで激論をかわす、近頃の若いもんは捨てたものでもない、熱い思いのおやじが身近に多数いることに驚く、このパワーは凄い。
私の地元星岡町では、おやじの会が中心となって防災訓練の一環として地域住民の防災意識の高揚と大規模災害時の安否確認の効率化を狙った黄色いハンカチプロジェクトを行っている。これは、大規模災害時、生存している御家庭には黄色い目印を玄関や窓等、外から見える場所に掲出していただき、掲げていない家庭への人命救助を重点化し、一人でも多くの地域の方の命を救おうという取り組みであります。自治会や公民館の役員は高齢者が中心、松山市が目指す住民自治の実現には若手の担い手の参加が必要です。そこで、地元、小学校と町内会のおやじの会の活動に最高齢者?として参加、飲みにケーションをはかりながらまちづくりについて時を忘れ深夜まで激論をかわす、近頃の若いもんは捨てたものでもない、熱い思いのおやじが身近に多数いることに驚く、このパワーは凄い。
第55回愛媛マラソン
 エントリー数は47都道府県と7つの国から11,324人、ボランティア3,200人、今回は公務員ランナー川内優輝選手効果もあり沿道には前年比1,500増の20万人の人出、経済波及効果は民間のシンクタンクの調査で4億7,600億円と過去最高を記録した。都市型になって初めての7年前の48回大会は、参加ランナーは3,488人、ボランティアは2,000人、経済効果は1億6,000万円だった。私は、本市が主催する当事業について、観光や健康、地域の活性化等 、スポーツが持つ多面的な効果を期待し、その拡充にむけて、議会でも何度も取り上げてきたテーマゆえ、喜びもひとしお、私も今回で19回目のチャレンジとなった。沿道の途切れることがなく延々と続く人垣、地域色豊かなだんじりや太鼓の応援、部活のユニフォーム姿の子ども達や学生の声をからしての声援、そしてゴールにはボランティアのハイタッチの人波には疲れを忘れるほどの感動を覚え、リサーチ通り過去最高の人出を実感した。今、ブームの都市型マラソン、健康志向と相まって、大変盛り上がりを見せ、全国各都市で趣向を凝らし行われている。今回、野志市長も終始笑顔で4回目の完走、2回目のチャレンジでサブフォー、3時間代で完走された西泉副市長、前日まで公務で海外、出張帰りの中村知事も途中全身けいれんというアクシデントに見舞われながらも持ち前の負けん気を発揮して完走、更には3時間30分切りのアスリート枠を達成された原副知事、県並びに県都のナンバー1、2がチャレンジ、しかも完走するという大会は恐らくこの愛媛マラソンだけではないか?まさに、オンリーワン、ナンバーワンの大会だ。警察や消防、マスコミ各社、公共交通機関、近隣店舗や住民、更にはボランティアの皆さん、惜しくも抽選に漏れた方等、関係各位のご理解とご協力に深く感謝したい。
エントリー数は47都道府県と7つの国から11,324人、ボランティア3,200人、今回は公務員ランナー川内優輝選手効果もあり沿道には前年比1,500増の20万人の人出、経済波及効果は民間のシンクタンクの調査で4億7,600億円と過去最高を記録した。都市型になって初めての7年前の48回大会は、参加ランナーは3,488人、ボランティアは2,000人、経済効果は1億6,000万円だった。私は、本市が主催する当事業について、観光や健康、地域の活性化等 、スポーツが持つ多面的な効果を期待し、その拡充にむけて、議会でも何度も取り上げてきたテーマゆえ、喜びもひとしお、私も今回で19回目のチャレンジとなった。沿道の途切れることがなく延々と続く人垣、地域色豊かなだんじりや太鼓の応援、部活のユニフォーム姿の子ども達や学生の声をからしての声援、そしてゴールにはボランティアのハイタッチの人波には疲れを忘れるほどの感動を覚え、リサーチ通り過去最高の人出を実感した。今、ブームの都市型マラソン、健康志向と相まって、大変盛り上がりを見せ、全国各都市で趣向を凝らし行われている。今回、野志市長も終始笑顔で4回目の完走、2回目のチャレンジでサブフォー、3時間代で完走された西泉副市長、前日まで公務で海外、出張帰りの中村知事も途中全身けいれんというアクシデントに見舞われながらも持ち前の負けん気を発揮して完走、更には3時間30分切りのアスリート枠を達成された原副知事、県並びに県都のナンバー1、2がチャレンジ、しかも完走するという大会は恐らくこの愛媛マラソンだけではないか?まさに、オンリーワン、ナンバーワンの大会だ。警察や消防、マスコミ各社、公共交通機関、近隣店舗や住民、更にはボランティアの皆さん、惜しくも抽選に漏れた方等、関係各位のご理解とご協力に深く感謝したい。
節目の年、幸先の良いスタートが切れた。愛媛マラソンに倣い、えひめ国体を筆頭に盛りだくさんのビッグエベントが、市民・県民総参加のもと、このように大盛会となり、地域が元気になることを期待したい。
欧州視察
 市議会欧州視察団に参加した。姉妹都市フライブルクを中心に1週間で、3ケ国、5都市を訪問した。当地は数十年ぶりの寒波が押し寄せており、日中でも気温は零下、厳寒の中、フライブルクではサロモン市長や市の幹部と両市の近況や今後の交流のあり方を意見交換、友好を確認し、各都市で、交通、観光、教育、福祉、環境の分野で先進的な取組みを体感し、大変有意義だった。本市の政策提言に大いに生かして行きたいと思う。特に、交通に関して、多くのまちではトラムや連結バスが中心街を頻繁に行き交い、多くの市民や観光客は時刻表を気にすることなく利用でき、また、時間限定の乗り放題運賃やゾーン運賃(距離制運賃)の制度は、まさしくハード・ソフトの両面から、市民の身近な足として機能していた。又、近代的な車両が教会や古城等、中世の建物群を縫うように走る風景そのものが観光資源として大きな役割を果たし、更に車両の色も雪の多いスイスのチューリッヒは白色、バルセロナは地中海を意識してか、青と白のツートン色に統一され、まちのイメージを醸し出す効果も演出していた。一方、郊外の拠点駅に駐車場を配置し、中心部への車の乗り入れや駐車場の設置、大型店の進出を規制する等、パークアンドライドやトランジットモールといった都市計画の施策が交通政策と有機的に結びつき、まちの魅力度向上に繋がっていた。しかし、こういった欧州各市の取り組みは順風満帆ではなく、少数意見や多様性を重んじる民主主義の先進地域が故に市民の合意形成には大変な時間と労力を要することも学んだ。サロモン市長からは、交通は様々な利害が輻輳する政策分野であり、特に日本と同じような自動車大国であるドイツでは、公共交通を優先する政策について市民の理解を得るには、大変な労力を要することも伺った。大切なことは、説明責任とリーダーシップ、だという言葉が心に強く残った。
市議会欧州視察団に参加した。姉妹都市フライブルクを中心に1週間で、3ケ国、5都市を訪問した。当地は数十年ぶりの寒波が押し寄せており、日中でも気温は零下、厳寒の中、フライブルクではサロモン市長や市の幹部と両市の近況や今後の交流のあり方を意見交換、友好を確認し、各都市で、交通、観光、教育、福祉、環境の分野で先進的な取組みを体感し、大変有意義だった。本市の政策提言に大いに生かして行きたいと思う。特に、交通に関して、多くのまちではトラムや連結バスが中心街を頻繁に行き交い、多くの市民や観光客は時刻表を気にすることなく利用でき、また、時間限定の乗り放題運賃やゾーン運賃(距離制運賃)の制度は、まさしくハード・ソフトの両面から、市民の身近な足として機能していた。又、近代的な車両が教会や古城等、中世の建物群を縫うように走る風景そのものが観光資源として大きな役割を果たし、更に車両の色も雪の多いスイスのチューリッヒは白色、バルセロナは地中海を意識してか、青と白のツートン色に統一され、まちのイメージを醸し出す効果も演出していた。一方、郊外の拠点駅に駐車場を配置し、中心部への車の乗り入れや駐車場の設置、大型店の進出を規制する等、パークアンドライドやトランジットモールといった都市計画の施策が交通政策と有機的に結びつき、まちの魅力度向上に繋がっていた。しかし、こういった欧州各市の取り組みは順風満帆ではなく、少数意見や多様性を重んじる民主主義の先進地域が故に市民の合意形成には大変な時間と労力を要することも学んだ。サロモン市長からは、交通は様々な利害が輻輳する政策分野であり、特に日本と同じような自動車大国であるドイツでは、公共交通を優先する政策について市民の理解を得るには、大変な労力を要することも伺った。大切なことは、説明責任とリーダーシップ、だという言葉が心に強く残った。