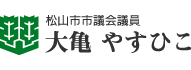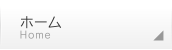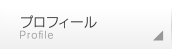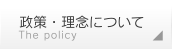ホーム > 月別アーカイブ: 3月 2009年
第16回関西学院大学文化講演会を開催しました
進取の国 アセアンの優等生“マレーシア”
 議会の海外都市行政視察でマレーシアを訪れた。錫と天然ゴムの国、発展途上国?そんなイメージしかなかった。しかし、クアラルンプール国際空港(KLIA)に降り立ち、自分の目で見たマレーシアは違った。まずは空港施設の設備に驚かされた。4,000m級の滑走路を2本備え、建物と、森林との調和が随所に見られるつくりになっており、マレーシアという国のイメージを打ち出した「森の中の空港」のコンセプトが体感できる。ガイドの説明によると黒川紀章氏が設計に携わり、日本の建設業者が関与しているとのこと。また、クアラルンプール市内は世界で二番目の高さの双子ビル(ペトロナス・ツイン・タワー)がまちのランドマークとしてそびえ、いたるところに近代的な外資系のオフィスビル、ホテル、そして国際級のコンペンション会場が建設され、また王宮、モスク等の伝統的な建築物も随所に見られ、新旧が見事に融合した近代都市であった。
議会の海外都市行政視察でマレーシアを訪れた。錫と天然ゴムの国、発展途上国?そんなイメージしかなかった。しかし、クアラルンプール国際空港(KLIA)に降り立ち、自分の目で見たマレーシアは違った。まずは空港施設の設備に驚かされた。4,000m級の滑走路を2本備え、建物と、森林との調和が随所に見られるつくりになっており、マレーシアという国のイメージを打ち出した「森の中の空港」のコンセプトが体感できる。ガイドの説明によると黒川紀章氏が設計に携わり、日本の建設業者が関与しているとのこと。また、クアラルンプール市内は世界で二番目の高さの双子ビル(ペトロナス・ツイン・タワー)がまちのランドマークとしてそびえ、いたるところに近代的な外資系のオフィスビル、ホテル、そして国際級のコンペンション会場が建設され、また王宮、モスク等の伝統的な建築物も随所に見られ、新旧が見事に融合した近代都市であった。
更に驚くべきことは、マハティール前首相の強力なリーダーシップのもと、2020年の先進国入りを目指すとのこと。それを具現化する都市像がサイバージャヤ(電脳都市)とプトラジャヤ(電子政府)である。サイバージャヤはITの研究・開発都市、プトラジャヤはすべてが電子化された電子政府の都市。世界の最先端の技術を結集させ、IT立国を目指そうとするもの。現在、連邦政府のほとんど機能がクアラルンプールからサイバージャヤに移転している。ITの先進都市像を目指しているところは数多く見受けられるが、サイバージャヤの建設の理念である3つの「共生」の考え方には特筆すべきところがあった。1つは人との共生。高い塀を取り除き隣近所で助け合える住環境をつくる。2つは自然との共生。森林の中に住居や企業が配置する。
風通しや周囲との調和を考え、建物も低くし、森林の中で冷暖房が要らないくらいの環境を目指す。3つは技術との共生である。このように、しっかりとした目標、理念を掲げて成長する国がマレーシアである。2020年、先進国の仲間入りをしたその国の姿をもう一度この目で確かめてみたいものである。
松山市子ども育成条例
 松山市議会史上初めてとなる2回の定例議会で継続審査となり、半年間にわたり議論され、最終的には、議会の文教消防委員会で修正案が作成され可決された「松山市子ども育成条例」について、私は、当該委員として深い関わりを持った。
松山市議会史上初めてとなる2回の定例議会で継続審査となり、半年間にわたり議論され、最終的には、議会の文教消防委員会で修正案が作成され可決された「松山市子ども育成条例」について、私は、当該委員として深い関わりを持った。
この間、マスコミ等でもその経過が大きく取りあげられ、また、賛成派、反対派の市民グループがシンポジウムや中央の識者を招聘しての勉強会等の開催により、市民の関心も非常に高いものとなった。
論点は、子どもを従来のような「保護の対象」として促えるのか、「権利行使の主体」として促えるのかという子ども観の違いにあり、どちらに軸足をおいた条例にするかで意見が分かれていたのである。
市民アンケート、参考人聴取、委員会での真摯な議論により、賛否両論の意見を取り入れた修正案を議会で取りまとめできたことで議会の存在感を示したことは大きな成果であり、またそれ以上にその事を通じて多くの市民にも子育てについて、再考するきっかけになったことは大変意義深いことであったように思う。今後は、条例の的確な施行により、子ども達や子育て中の保護者を社会全体で支援し、元気と勇気を与えるものとなるようにしっかり見届けて行こうと思う。
同窓会活動支援による地域貢献
私の母校、関西学院大学(兵庫県宮西市)は中予地区に約300名の同窓生を有し、私は同窓会の諸活動のお世話役の1人として関りを持たせて頂いている。その方針の1つに地域貢献を掲げており、年1回、本学の教授を招き、地域住民に関学の学術・文化・教養に接し、自己啓発・自己研鑚に励んでもらおうという趣旨で市民公開講座を開催している。
これまで、「地方分権時代の地方自治制度のゆくえ」と題した講演、あるいは松山市の「坂の上の雲まちづくり」にちなんで、司馬遼太郎さんの文学や歴史観をテーマにした講演会を実施し、沢山の市民の皆さんにご参加いただき、好評を博した。また、現役学生で構成するグリークラブ(明治32年創部の日本最初の男性合唱団)が松山を訪問。療養所や高齢者施設で、愛大附属小のコーラス部と共演。日本有数の歴史と実績を誇る大学生と小学生の初の共演が松山で実現。施設利用者のみならず、地域、ご父兄の皆さんにもお越し頂き、会場は満員の大盛況。大学生の体の芯にまで響く低音と小学生の澄み切った高音がうまくミックスし、聴衆を魅了。
今後、少子化の影響で大学経営も一層困難になることが予想され、事実経営難から閉校となる大学も出てきており、京阪神の大学とは言えども、地方に受け入れられる最高学府として、また地方の文化向上の為にも、同活動を支援して行きたいと思う。
夢に向かってチャレンジ
 継続するは力なり、1つの目標を掲げ、それに向かって努力することで、人生は豊かなものになる。更に目標を達成できれば、よりベターである。私は、自身の健康管理、そして常にチャレンジャー精神を持ち続けたいとの願いから、毎年愛媛マラソン大会に出場しフルマラソンに挑戦している。更に旧中島町と合併し初めてのトライアスロン中島大会にも初挑戦した。
継続するは力なり、1つの目標を掲げ、それに向かって努力することで、人生は豊かなものになる。更に目標を達成できれば、よりベターである。私は、自身の健康管理、そして常にチャレンジャー精神を持ち続けたいとの願いから、毎年愛媛マラソン大会に出場しフルマラソンに挑戦している。更に旧中島町と合併し初めてのトライアスロン中島大会にも初挑戦した。
水泳1500m、自転車40km、ラン10kmの過酷なコース、参加者は、島内外から選手約400名、そしてボランティアはなんとその2倍の800名。彼らと同じ土俵で、完走という同じ目標に向って、時には競いあい、励ましあいながら汗をかき、更に島民の皆さんの心温まる声援にも後押しされ、無事完走。
また、鯛やヒラメの刺身、タコ飯、みかん等の食にも大満足。20年前に島の有志数名で立ち上げたこのイベント、台風、渇水、サメ騒動等幾度の困難にも負けず、回を重ねる度に盛況になり、今では中島地域の1つの伝統となり、文化となっている。
原点は島の人達の故郷を思う熱い心。関係各位に感謝と敬意の気持ちを表し、中島地域のスポーツをテーマのまちづくりが、新松山市の財産として更に発展することを祈念したい。今後も、チャレンジャー精神で何事にも取り組んで行きたい。
沖縄の地にて平和を思う
 「百聞は一見にしかず」。現在、インターネットの普及で全世界のあらゆる情報が簡単に机上で入手できるようになった。しかし、現地に赴き、自分の目で見る、まちの雰囲気を身体で感じることが、1番の勉強になる。
「百聞は一見にしかず」。現在、インターネットの普及で全世界のあらゆる情報が簡単に机上で入手できるようになった。しかし、現地に赴き、自分の目で見る、まちの雰囲気を身体で感じることが、1番の勉強になる。
行政視察は、議員としての重要な活動の1つだ。私が経験した視察の中で特に印象に残った場所は沖縄である。沖縄は、第二次世界大戦において日本で唯一、地上戦が行われたところ。戦没者は約20万人に上り、その内住民が約9万4千人、実に県民の2割が犠牲になったのである。更に現在においても「基地の島」と呼ばれており、県の面積が日本全土の0.6%でありながら、日本にある米軍基地の75%が沖縄に集中している。まちの中心部の広大な平地に4,000メートル級の滑走路2本を備え戦闘機が離発着訓練を繰り返している嘉手納米軍基地を高台から眺め、また日中耳をつんざくばかりの爆音とともに軍用ヘリが行き交う。 市民生活に及ぼす影響は多大だ。
これが本当に戦後60年、平和国家日本の姿なのかと目を疑った。今、イラクや北朝鮮問題等を通して国際社会の中で日本が果たす役割について議論がなされ、更に戦後60年の節目を迎えて、今後の日本の道標となる憲法改正問題がクローズアップされている。憲法改正となると国民投票となり、私達1人ひとりが自らの責任で権利を行使しなければならない。
私を含め、戦争を知らない国民が大半を占める今、国民1人ひとりが戦争の真実を学び、子々孫々まで持続可能な日本の将来について真剣に向き合わねばならない時期にきていることを認識した。
交通まちづくり
 増え続ける車、自動車は現代人の夢を実現した。いつでも、どこへでも自由に早く行き着くことができ、人の行動、そして物流をこれほどの広がりで解き放った乗り物は今までかつてなかった。自動車は20世紀の技術が人間に与えてくれた最高の贈り物だと言われたこともあった。
増え続ける車、自動車は現代人の夢を実現した。いつでも、どこへでも自由に早く行き着くことができ、人の行動、そして物流をこれほどの広がりで解き放った乗り物は今までかつてなかった。自動車は20世紀の技術が人間に与えてくれた最高の贈り物だと言われたこともあった。
ところが、21世紀を迎えた今、まちは車であふれている。これによってもたらされた環境汚染や交通渋滞、交通事故、さらには物流や人的交流の停滞による経済競争力の低下、中心商店街の衰退等の負の遺物に、私たちは今、健康で安全に生きるために、自動車の利用を減らし、環境に優しく、渋滞や事故のない、人が歩き・集える安全で移動しやすいまち、すべての人が利用しやすい公共交通が整備されたまちを目指し真剣に考えなければならない。幸いにも、松山市は築城 400年を誇る松山城を中心とし、街路が機能的に整然と区画され、官公庁や金融機関、商店街、医療機関、更に子規や漱石等の文化人のロマン漂う足跡が残る史跡が集積し、それらを線で結ぶように路面電車やバスの公共交通が走り、更に起伏が少ない地形は徒歩や自転車での移動にも適した都市形態である。
私は、交通政策をまちづくりの1つの柱として捉え、行政機構の中で従来の交通行政の縦割りを是正し一本化して扱う総合交通課の新設、四国初のオムニバスタウン、まつちかタウンのバリアフリー化推進等に積極的に関わりを持たせて頂いた。
のびのび元気な人づくり
 松山海洋少年団は、昭和43年発足。現在小学三年生から高校三年生迄約40名の子ども達が活動しており、私は父母の会でお世話をさせて頂いている。四方を海に囲まれた海洋国日本、古来わが国は、外国との交易、魚介類や天然資源等、海から数々の恩恵を受けてきた。
松山海洋少年団は、昭和43年発足。現在小学三年生から高校三年生迄約40名の子ども達が活動しており、私は父母の会でお世話をさせて頂いている。四方を海に囲まれた海洋国日本、古来わが国は、外国との交易、魚介類や天然資源等、海から数々の恩恵を受けてきた。
海洋少年団は、万物の母なる海を舞台として、手旗信号、水泳、ポート等の海洋訓練、海浜清掃や災害復旧等の奉仕活動、国際交流など多様な体験活動を通じ、海洋に関する科学的知識・技術の習得や環境保全等の地球規模の課題への取組、社会生活に必要な徳性の涵養を深めることにより健全な人格の育成を目的としている。
昨今の少年犯罪の多発・凶悪化は、親、兄弟、友達等とのコミュニケーション、憤りや不満をコントロールし、それをいかに自分の成長につなげるかの手段を持っていないことに起因するものである。一方、海洋少年団での団体生活では、厳しい規律のもとで躾を身に付け、礼儀を教わり、友情を育み、そして団結心を養うのであるが、これらの教えは、その後の人格形成にも大きく影響してくるものである。事実、海洋で育った子ども達は、皆、元気にすくすくと育ち、希望の進路にも進み、現在多くの人材が社会の第一線にて活躍している。そのことを考えると、少年時代に経験した団体活動への参加は青少年教育の大きな柱と言える。
私は、海洋の活動を通して、21世紀を迎えた今、日本人の心から忘れられようとしている躾と礼儀の尊さ、大切さ、有意義さを改めて見直し、その心を取り戻すお手伝いができればと願っている。